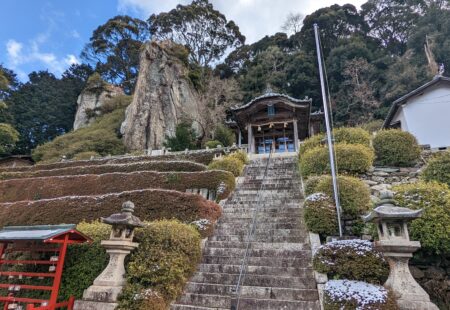京の街の「かつて」を想像する
京阪電車の清水五条駅をから地上へ上がり、観光客でごった返す東山へは向かわず、そのまま五条通で鴨川を超え、麩屋町通を北へ上がる。
ほどなく右手に、通り過ぎてしまうくらい規模の小さい神社があった。かつて朝日神明社と呼ばれた朝日神明宮だ。
小さな神社とはいえ、石畳があり、釘貫門も鳥居も立派である。京都市による案内板も立てられている。
案内板の説明には『社伝によれば、貞観年間(858〜876)に丹波国桑田郡穴生村(現在の亀岡市)に造営され、元亀3年(1572)に現在地に遷座されたといわれている』とあり、これは、京都の書店・吉野家から安永9年(1780)に刊行された『都名所図会』、その天明6年(1786)再板本(国際日本文化研究センター公開)の記載とも一致する。
同じく説明には『天照大神を祭神とし、かつては、南北は五条通から松原通、東西は河原町通から富小路通に至る広大な社域を有し、「幸神(さいのかみ)の森」と呼ばれた』とある。
南北が通り2本分、東西は通り3本分というと、当地の区分けで7ブロック分だ。
なお、『都名所図会』の記述には朝日宮と神明宮とがあり、朝日宮の由緒が朝日神明宮と同じなので、もしかすると、広大な神域の中に、ふたつの社があったのかもしれない。
ちなみに幸神の森とは、近世の京都にあった七つの森のひとつのよう。
もっともこの頃の京都には、江戸時代初期に水雲堂孤松子(すいうんどうこしょうし)が著した京都の観光案内本『京羽二重』では17の森が記載されているし(幸神の森は入っていない)、山城国には山城八森と呼ばれる森があったりしたので、選者・著者または彼らの情報入手先によっていろいろな“くくり”があったのだと思われる。
現在は完全に姿を消しているが、その当時はここに森があった、のだなぁ。
想像すると途端に、町屋が並ぶ先に深い森が見える、心地よい景色が広がる。
歴史は人が守り、伝えていく。
社域が広大だった頃は、竈神社、稲荷社、祓川(はらいかわ)社、恒情(こうじょう)神社、人丸(ひとまろ)社、飛梅天神、八幡春日社、猿田彦社の8末社があったというが、天明8年(1788)の天明の大火、元治元年(1864)の禁門の変による兵火で大半が焼失してしまった。唯一残ったのは猿田彦社(幸神社)だけで、現在の社殿の裏にひっそりと、神石二個が安置されている。
小さき社ではあるが、夏のはじめには茅の輪が設置され、月並祭、元旦祭、毎年9月16日には大祭も執り行われる。現在の社域は小さいながらも、とても清く保たれているように感じる。地面は掃き清められ、手水鉢、掲げられた額、それらに汚れはない。
毎年夏越しの大祓の際には地域の皆さんが茅の輪をくぐりに訪れるそうで、この社を地域になくてはならない存在として、丁寧に、丁寧に、地域の人々が守ってくださっているのだ。
開発、変化とは別次元で、まちとその文化の時を感じよう。
この朝日神明宮のように、かつては広大な敷地を有していたが現在はこぢんまり、という社寺は少なくない。都市部においてはなおさらである。
近年では諸事情により、社寺自らが敷地を別の活用法で維持している例もあり、周辺の開発などとも相まって、社寺が社域・寺域を含め中世や近世の面影を残していることは多くない。
それでも、説明文や周辺の石標、道祖神、町屋の並び、露地の曲がりくねった様などから、少し昔のことを想像することができる。
想像できると、その痕跡を訪ね歩いてみようかしら、なんて、足が前に出、心が動き出す。
その頃のまちで暮らして板人々の目線に思いを馳せることもできる。
旅って、そんなことが面白い。